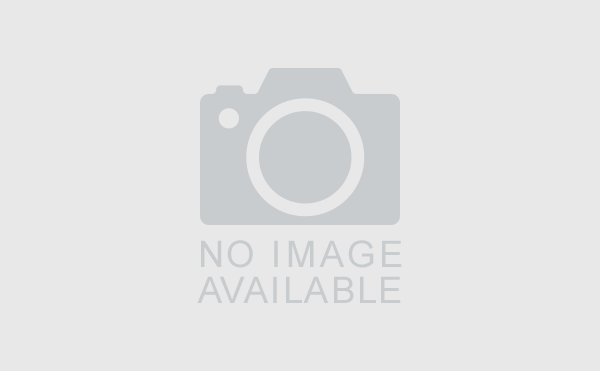コンプレッサーの種類
コンプレッサー(Compressor、圧縮機)は、気体(冷媒ガスや空気など)を圧縮し高圧のガスを作り出す装置をいう。空調分野では、冷凍機や空調機の内部部品として冷媒ガスを圧縮し、熱交換サイクルに利用されている。生産分野では、大気中の空気を圧縮し高圧化することで、電気に代わる動力源や乾燥ブローとして利用されている。
ここでは空気を圧縮する機械としてのコンプレッサーについて記載する。
コンプレッサーの形状による分類
コンプレッサーは仕組みによって大きくターボ型と容積型に区別される。動翼によって空気に速度エネルギーを与えて、それを静圧に変換する仕組みのものをターボ型、ピストン運動などによって空気の容積を小さくする(圧縮する)ことで高圧化する仕組みのものを容積型という。コンプレッサーの形状によりさらにターボ型は遠心式・軸流式・斜流式・横流式、容積型はスクリュー式・スクロール式・ロータリー式・レジプロ式に細分されている。
ターボ型は仕組みが単純で大型化も容易であるが、負荷変動への細かい容量調整は容積型に劣る傾向にある。ターボ型は、圧縮の仕組みはファン(送風機)と同じ仕組みであり、ファンとの違いは圧力比(出口圧力/入口圧力)であり、圧力比が1.1未満のものをファン、それ以上のものをコンプレッサーという。
※以前はファンのほかブロア(圧力比1.1以上2.0未満)も送風機の一部とされていたが、2005年にJIS B0132が改正され現在ではブロアは圧縮機の一部とされている。
ターボ型
| 形状分類 | 風圧方向 | 特徴 |
|---|---|---|
| 遠心式 | 中央から吸い込み、遠心方向に吐出する。 | 風量は小さい、大きい圧力を得られる。 |
| 軸流式 | 中央から吸い込み、反対中央方向に吐出する。 | 圧力は小さい、大きい風量を得られる。 |
| 斜流式 | 中央から吸い込み、反対中央広がり方向に吐出する。 | 遠心式と軸流式の中間性能を持つ。 |
| 横流式 | 横から吸い込み、反対横方向に吐出する。 | 小口径でも効率の低下は少なく、横方向に長く安定した風量を得られる。 |

遠心式 |

軸流式 |

斜流式 |

横流式 |
容積型
| 形状分類 | 構造原理 | 特徴 |
|---|---|---|
| スクリュー式 | 雄雌の2本のスクリューが回転し、スクリューの溝(空気室)が徐々に小さくなることで軸方向に圧縮する。 | 連続した運動に適しており、工場などで最も利用されている。脈動が小さく、音や振動も小さい。 |
| スクロール式 | 渦巻型の可動スクロールが回転し、スクロール内の空気室が徐々に小さくなることで外側から中央方向に圧縮する。 | 効率に対してコンパクト、脈動が小さく、音や振動が最も小さい。 |
| ロータリー式 | ローターが偏心回転し、シリンダの回転により空気を小さくし圧縮する。 | 小型でも高効率、風量は小さい。脈動が小さく、音や振動も小さい。 |
| レジプロ式 | 回転運動を直線運動に変換し、ピストン運動により空気を小さくし圧縮する。 | 小型でも高効率、圧縮効率が高い。脈動が大きく、音や振動も大きい。 |

スクリュー式 |

スクロール式 |

ロータリー式 |

レジプロ式 |
コンプレッサーの排熱と冷却方法
コンプレッサーでの圧縮動作は、外部との熱のやり取りが無い状態で気体の体積を小さくする断熱圧縮に近い現象※が起きるため、高圧化と同時に温度上昇が発生してしまう。よって圧縮機には冷却機能を設ける必要がある。冷却方式により、空冷式と水冷式の2つに分類される。
・ボイル・シャルルの法則:PV/T=一定
P:圧力
V:容積
T:温度
・熱力学第一法則:Q=ΔU+W
Q:外部から気体に加えた熱量
ΔU:気体の内部エネルギーの増加量
W:外部にした仕事
以上2つの法則により、理想気体において圧縮運動時に
シリンダ内部に発生した熱が外部に完全に放出される場合(ΔU=0)は、等温変化(T=一定)よりP×V=一定となる。
シリンダ内外での熱のやり取りが無い場合(Q=0)を、断熱変化という。実際のコンプレッサーでは等温変化と断熱変化の中間程度の変化状況になる。
水冷式コンプレッサー
水冷式とは、コンプレッサー内部に冷却水を取り込みコンプレッサーを冷却する方式をいう。水は空気に対して約4倍の比熱(水:約4.18J/gK、乾燥空気:約1.006J/gK)をもつため空気の約4倍の冷却能力をもつため空冷式より効率よく冷却が可能である。冷却水を循環させる場合は、冷却塔などを設けて室外で冷却水の放熱をする必要がある。
コンプレッサー内部に冷却水を巡らせる必要があるため空冷式より煩雑になるが、吐出空気温度や潤滑油などの冷却をも行うことができる。
空冷式コンプレッサー
空冷式とは、コンプレッサー周辺の空気(外気)を取り込みコンプレッサーを冷却する方式をいう。室内に排熱を放出すると室内が高温になっていくため、屋内にコンプレッサーを設置する場合は排熱を外部に放出する必要がある。コンプレッサー排熱を外部に放出する機能として、別途送風機(ファン)や風道(ダクト)が必要になる。
外気温度によって排熱量が変動してしまうため、外気温度が高くなるにつれて効率が下がっていってしまう。さらに高温になるとオーバーヒート(コンプレッサーの保護のため、周辺空気が40℃以上になった場合にコンプレッサーが緊急停止する機能)が起きる可能性が高まってしまう。
コンプレッサーオイルとドレン処理
コンプレッサードレン
コンプレッサーは大気中の空気を圧縮しているので、体積あたりの水蒸気量が大きくなり、さらに高圧化もするので露点温度も上昇し、一部水蒸気は結露水(ドレン水)となってしまう。コンプレッサー計画ではこの結露水の処理についても検討する必要がある。
また、大気中に含まれている水蒸気量は常に一定ではなく、夏期は高温多湿のため水蒸気量が多くなり、冬期は温度低下著しいため水蒸気の凝固(結露)が多くなり、さらに温度が下がると凍結してしまう可能性も考慮しなくてはならないので各時期のドレンの排出を計画する。
コンプレッサーオイル
コンプレッサーの摺動部の金属の摩耗を防止・空気漏れシールのため潤滑油(オイル)を定期的に注入する必要がある。コンプレッサー内部に潤滑油の注入することにより圧縮空気中にもオイルが含有する。コンプレッサードレンについても同様にオイルを含むものになり、この廃水は油水分離器などのドレン処理装置を用いない限り産業廃棄物として処理する必要がある。
オイルフリーコンプレッサーについて
コンプレッサーは一般仕様の給油式コンプレッサーと、食品や医療品、半導体製品などの圧縮空気の利用で、圧縮空気中のオイルミストの含有が許容されない(クリーンエアが求められる)場面において利用されるオイルフリーコンプレッサーとがある。オイルフリーコンプレッサーには躍動部をチップシールなどで表面処理することで金属同士を非接触とするタイプと、躍動部に潤滑油を利用した上で特殊被膜などで圧縮空気室内にオイルが入らないタイプとがある。
どちらのオイルフリーコンプレッサーにおいても給油式と比較し、部品が多く煩雑になる。また、潤滑油を使用しないオイルフリーコンプレッサーにおいては給油式より能力が落ちる傾向にあり、同じ公称出力のコンプレッサーであればオイルフリーは、給油式の70~90%程度の効率となる。
参考予定:エアドライヤー・油水分離器、配管オイル