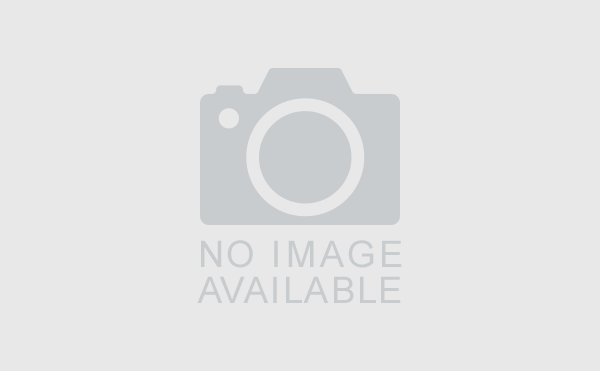配管材における銅について
銅は古くから様々な用途に利用されてきた金属であり、配管分野においては純銅(リン脱酸銅)は配管や継手に、銅合金(青銅や黄銅)はバルブや継手などに幅広く使用されている。また、金属の中で銀に次いで熱伝導性が高いため、空調分野の熱交換器コイルに最も利用されている金属でもある。
銅管の特徴
銅管は、鋼管やステンレス鋼管などの他の金属系配管と比較し加工性が高く、耐熱性と耐食性に優れている。価格もステンレス鋼管と同様に高価ではあるが、銅はリサイクルにかかる工程が少なく安価に再生可能のためスクラップの買取価格がステンレスより高い。
銅管は潰食により小さな穴が開く(ピンホール現象)が発生しやすく、以前は衛生配管(主に給湯配管)で多く利用されていたが、現在ではステンレス鋼管の台頭により衛生配管でのシェアは奪われつつある印象にある。現在は空調機の冷媒ガス配管や医療ガス配管に主に利用されている。また銅は腐食すると青錆(緑青)が発生するが、鋼管やステンレス鋼管などの鉄系金属が腐食すると発生する赤錆と異なり、給水や給湯に溶け出すトラブルは少ない。
空調機の冷媒ガス配管は現在は銅管が主流であるが、近年はアルミニウム配管による冷媒ガス配管システムが徐々に増加している。銅の世界的な需要の高まりにより、銅配管の安定した供給が難しくなりつつある現状を解決できる配管材の一種としてアルミニウム配管に注目が集まっている。アルミニウムは加工性がよく、熱伝導率が高く、リサイクル性が高いといった銅管に似た特徴をもつ。(アルミニウムの熱伝導率は約230W/mK、銅の熱伝導率は約400W/mKであり、銅管のほうが熱伝導率は高く、加工性も銅管のほうがよい。)
アルミニウムは銅と比較し、軽量で安価(配管材としてはまだ新素材の部類であり比較的高価な傾向にある。)で腐食に強いが、銅管に比べて強度が低く、銅管と同強度とするためには配管が厚くなるほか、アルミニウムが溶接が難しい材料とされている。(アルミニウム配管による空調システムはメカニカル継手が主流となる。)
銅管の種類
配管用銅管
銅管は、日本工業規格でJIS H3300で規格されており、このうち水道用銅管は公益社団法人の日本水道協会でJWWA H101、冷媒用断熱材被覆銅管は一般社団法人の日本銅センターでJCDA0009・JCDA0010に規格されている。
銅管の接続方法は、主に継手によるものとろう付けによるものがある。継手によるものには、配管をフレア加工し接続する継手、プレス(圧着)によりかしめる継手、はめ込みで接続できるメカニカル継手などがある。
ろう付けには、軟ろう付(はんだ、ソルダー接合とも)と堅ろう付がある。堅ろう付は融点が450℃以上の溶加材を用いるもの、軟ろう付は融点が450℃未満の溶加材を用いるものをいう。一般に給湯管は軟ろう付、冷媒管は堅ろう付で施工されている。なお、上水に利用する場合は鉛の利用されていない鉛レス(鉛フリー)のろう材を利用する必要がある。
建築用銅管
銅を主原料につくられた銅継目無管を銅管(配管用銅管)といい、そのうち建築用途全般での利用を想定された銅管を建築用銅管という。建築用銅管はJIS H3300で規定されており、規格の後に銅の種類により合金番号を表示する。例えば、JIS H3300-C1220Tはリン脱酸銅を利用した銅管の規格になる。現在指定されている合金は無酸素銅C1020、タフピッチ銅C1100、リン脱酸銅、 高耐食銅C1260、高強度銅、丹銅、黄銅、復水器用黄銅、復水器用白銅がある。
銅管には肉厚と材質による種別が存在する。
肉厚種別は3種類あり、Mタイプが標準、Lタイプが肉厚、KタイプはLタイプよりさらに肉厚になる。Mタイプは一般配管用とされ、主に給水や給湯、冷温水や都市ガスなどに利用される。Kタイプは医療配管用、LタイプはMタイプとKタイプの中間としてどちらの用途にも使用される。
材質種別は4種類あり、硬い順にH>1/2H>OL>Oである。H材はハード材(硬材)で、強度が高く曲げ加工は難しい材料であり、給湯配管などに利用されている。1/2Hは半硬材で、ベンダーを利用すれば曲げる程度の硬さであり、冷媒配管直管や医療ガス配管などに主に利用されている。OL材・O材はなまし材で、手曲げが可能なくらい柔らかい材料であり、冷媒配管の接続部(コイル材)として主に利用されている。巻き銅管なので10m・20m・100mなどと1本(1巻)あたりの長さを直管(定尺4m、5mもある)より長くとることができる。
JIS H3300 表15 配管用管及び水道用銅管の寸法及び平均外径の許容差
| 呼び径a) | 寸法 | 平均外径の 許容差C) | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| (A) | (B) | 外径 | 肉厚 | |||
| Kタイプb) | Lタイプb) | Mタイプb) | ||||
| 8 | 1/4 | 9.52 | 0.89 | 0.76 | 一 | ±0.03 |
| 10 | 3/8 | 12.70 | 1.24 | 0.89 | 0.64 | ±0.03 |
| 15 | 1/2 | 15.88 | 1.24 | 1.02 | 0.71 | ±0.03 |
| 一 | 5/8 | 19.05 | 1.24 | 1.07 | 一 | ±0.03 |
| 20 | 3/4 | 22.22 | 1.65 | 1.14 | 0.81 | ±0.03 |
| 25 | 1 | 28.58 | 1.65 | 1.27 | 0.89 | ±0.04 |
| 32 | 1 1/4 | 34.92 | 1.65 | 1.40 | 1.07 | ±0.04 |
| 40 | 1 1/2 | 41.28 | 1.83 | 1.52 | 1.24 | ±0.05 |
| 50 | 2 | 53.98 | 2.11 | 1.78 | 1.47 | ±0.05 |
| 65 | 2 1/2 | 66.68 | 一 | 2.03 | 1.65 | ±0.05 |
| 80 | 3 | 79.38 | 一 | 2.29 | 1.83 | ±0.05 |
| 100 | 4 | 104.78 | 一 | 2.79 | 2.41 | ±0.05 |
| 125 | 5 | 130.18 | 一 | 3.18 | 2.77 | ±0.08 |
| 150 | 6 | 155.58 | — | 3.56 | 3.10 | ±0.08 |
注
a)呼び径は、(A)又は(B)のいずれかを用いる。ただし、必要に応じて(A)による場合にはA、(B)による場合にはBの記号をそれぞれの呼び径の後に付けて区分する。
b)Kタイプは、主として医療配管用、Mタイプは、主として水道、給水、給湯、冷温水及び都市ガス用であり、Lタイプは、その両方の用途に用いる。
c)平均外径の許容差とは、管の任意の断面で測った最大外径と最小外径との平均値(平均外径)と外径との差の許容限界をいう。
水道用銅管
銅管(配管用銅管)のうち、給水装置分野で使用する銅管は主に水道用銅管が利用されている。水道用銅管は日本水道協会規格JWWA H101で規定されている。以前は1形(ミリサイズ)と2形(インチサイズ)の規格があったが、現在は旧2形のみが規定され、ミリサイズ銅管は1形から派生しコントロール銅管などに利用され、水道用ミリサイズ銅管としてJBMA T203と規定されている。
建築用銅管より規格範囲が狭い(Kタイプは無し、Mタイプは10A~50A、Lタイプは8A~50Aまで)が外径や肉厚等の条件は同じである。現在は、リン酸銅を利用した銅管のみが水道用銅管に規格されている。
水道用銅管は被覆材付銅管も規定されており、Pタイプ(低発砲ポリエチレン(発泡倍率約2倍)+表皮ポリエチレン樹脂)と、Vタイプ(断熱空気層+塩化ビニル被覆)がある。Pタイプは外圧に強く、Vタイプは保温厚が薄いため省スペースというメリットがある。
耐孔食性銅管類
銅管はピンホール現象などによる漏水が発生しており、その対策品として耐食性を向上させた銅管を各社開発している。主な耐孔食性銅管としては、耐孔食性銅合金管・管内面スズ被覆銅管(STC銅管)の2種類があげられる。
耐孔食性銅合金管
耐孔食銅合金管は、銅管に特殊金属(Cu-Sn-Zr-P系合金。Cu銅、Snスズ、Zrジルコニウム、Pリン)を加えることで耐食性を高めた銅管である。特殊金属の添加量は合計でも1%未満であり、リン脱酸銅継目無管とほぼ同様な取扱いが可能である。主な製品はピコレス(株式会社KMCT)で日本水道協会基本基準認証品であるため水道用銅管の代替品としての使用が可能である。
管内面スズ被覆銅管(STC銅管)
管内面スズ被覆銅管(STC銅管、スーパーティントコート)は、銅管内面にSn(スズ)をコーティングすることで保護被膜の役割を果たし、銅イオンの溶出を極めて低く抑えることで、耐食性を高めた銅管である。主な製品は建築配管用STC銅管スーパーティンコート(NJT銅管株式会社)であったが、2025年4月をもって販売終了となる。
冷媒用断熱材被覆銅管
冷媒用断熱材被覆銅管は、主に空調機の室内機と室外機をつなぐ冷媒ガス配管用に使用される銅管に、断熱性の向上や結露防止のために保温材がセットされた配管である。冷媒用断熱材被覆銅管は一般社団法人の日本銅センターでJCDA0009・JCDA0010に規格されている。保温材の材質は主に発砲ポリエチレンで、表皮はポリエチレンフィルムである。前述の水道用銅管の被覆銅管と異なり、冷媒用銅管はインチサイズ(B)に対してミリサイズ(a)がワンサイズ低いので注意が必要である。
JCDA0009 表5・表6 断熱材被覆銅管の寸法(呼び径追記)
| 呼び径 | 原管平均外径 | 原管肉厚 | 原管質別 | 断熱材の厚さ | コイル巻管長さa)b) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液管 | ガス管 | |||||
| 1/4 | 6.35 | 0.80 | O 又は OL |
10.0以上 | 20.0以上 | 20,000 +600 -0 |
| 3/8 | 9.52 | 0.80 | ||||
| 1/2 | 12.7 | 0.80 | ||||
| 5/8 | 15.88 | 1.00 | ||||
| 3/4 | 19.05 | 1.20 | ||||
注a)コイル巻き長さは、受渡当事者間の協議によって変更することができる。
注b)コイル巻管長さは、銅管長さとする。
| 呼び径 | 原管平均外径 | 原管肉厚 | 原管質別 | 断熱材の厚さ | 直管長さa)b) | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 液管 | ガス管 | |||||
| 1/4 | 6.35 | 0.80 | 1/2H 又は H |
10.0以上 | 20.0以上 | 4,000 +50 -0 |
| 3/8 | 9.52 | 0.80 | ||||
| 1/2 | 12.70 | 0.80 | ||||
| 5/8 | 15.88 | 1.00 | ||||
| 3/4 | 19.05 | 1.05 | ||||
| 7/8 | 22.22 | 1.20 | ||||
| 1 | 25.40 | 1.35 | ||||
| 1 1/8 | 28.58 | 1.55 | ||||
| 1 1/4 | 31.75 | 1.70 | ||||
| 1 3/8 | 34.92 | 1.85 | ||||
| 1 1/2 | 38.10 | 2.00 | ||||
| 1 5/8 | 41.28 | 2.15 | ||||
| 1 3/4 | 44.45 | 2.30 | ||||
| 2 | 50.80 | 2.65 | ||||
| 2 1/8 | 53.98 | 2.80 | ||||
注a)直管長さは、受渡当事者間の協議によって変更することができる。
注b)直管長さは、銅管長さとする。
JCDA0009とJCDA0010規格は、材料の種類は同じであるが、最高使用圧力(設計圧力)と原管肉厚と保温厚みの規定が異なる。材料種類は、銅管はJIS H3300の無酸素銅(C1020)リン脱酸銅(C1201・C1220)、保温材種類はJIS A9511、保温材の難燃性能はJIS C3005に規格されている。JCDA0009は、国土交通省の「公共建築工事標準仕様書」に掲載規格であり、最高使用圧力(設計圧力)は4.3MPa以下、ガス管の保温厚は20mm以上である。JCDA0010は、最高使用圧力(設計圧力)は4.80MPa以下~3.45MPa以下で3種別の区分があり、原管の平均外径及び使用冷媒圧力ごとに原管肉厚及び断熱材の最低・最高厚さを規定している。
青銅や黄銅の継手やバルブについて
青銅と黄銅は、銅管を利用しない配管システムにおいても幅広く利用されており、配管分野で最も触れる機会の多い銅合金である。バルブのボディや水栓金具(通常は防錆加工で、ニッケルクロムメッキなどのメッキが施されている。)、塩ビ継手やコア入り継手の水栓ソケットなどにも利用されている。こちらも銅管と同様に上水に利用する場合は鉛レス(鉛フリー)のものを利用する必要がある。
銅はステンレスとイオン化傾向が同程度のため、ステンレス配管に利用しても異種金属接触腐食が発生しにくい。
 青銅弁
(参考:株式会社キッツ) |
 黄銅弁
(参考:株式会社キッツ) |
青銅(砲金)について
青銅(砲金)は、銅にスズを5%程度添加した銅合金である。強度や耐食性が高く、色は茶色に近いくすんだ色で10円硬貨の材料にも使用されている。青銅製のバルブは青銅弁としてJIS B2011規格されている。
青銅合金には、Cu-Sn-Zn-Pb系(鉛入り合金、被削性が高い)、Cu-Sn-Zn系(鉛フリー、耐食性が高い)、Cu-Sn-Zn-Ni-S系(鉛フリー、鉛入りと伸び引張強さは同等、被削性は鉛入りに劣る)のほか、青銅より硬いリン青銅Cu+Sn+P系(鉛フリー合金、耐食性が高い)などがある。
黄銅(真鍮)について
黄銅(真鍮)は、銅に亜鉛を40%程度添加した銅合金である。強度や耐食性は青銅には劣るが、加工性は青銅よりも高く、色は金色に近い光沢色で5円硬貨の材料にも使用されている。黄銅製のバルブは各メーカーで規格品による。
黄銅合金には、Cu-Zn-Pb系(鉛入り合金、被削性が高い)、Cu-Zn系(鉛フリー、強度が低い)、Cu-Sn-Pb-Ni-Si系(機械的性質の改良)などがある。